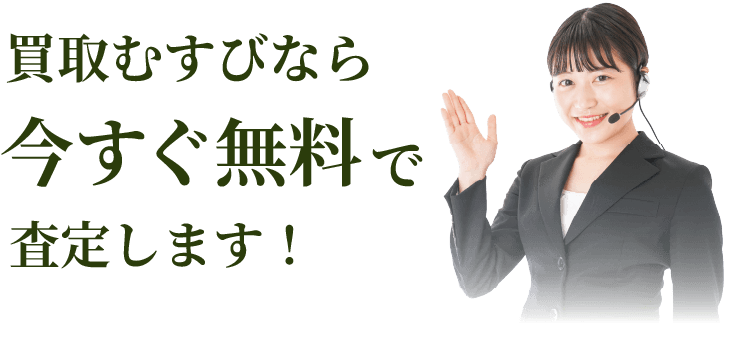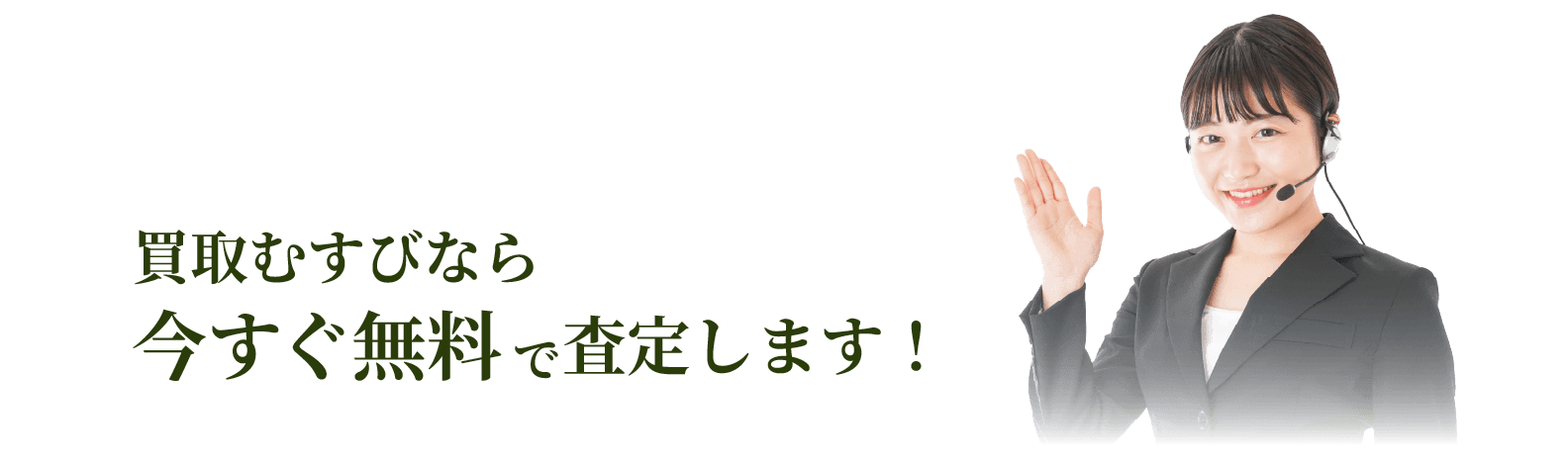執筆:
買取むすび 編集部
【時代別】明治・大正・昭和の有名な日本人画家と現代アートの巨匠を紹介

「有名な日本人画家はだれ?」
「絵画の魅力や楽しみ方を知りたい」
このように考えていませんか。
絵画に興味はあるものの有名な日本人画家がわからず、美術館に行ったり、アートを購入したりすることを迷っている方もいるでしょう。
本記事では、時代別の有名な日本人画家と現代アートの巨匠を紹介します。
絵画の価値を決めるポイントや絵画鑑賞の楽しみ方も解説するため、ぜひ参考にしてみてください。
目次
明治の有名な日本人画家

日本の有名画家を時代別に紹介します。まずは、明治の有名画家を見ていきましょう。
- ・横山大観(よこやまたいかん)
- ・菱田春草(ひしだしゅんそう)
- ・竹内栖鳳(たけうちせいほう)
- ・下村観山(しもむらかんざん)
- ・上村松園(うえむらしょうえん)
ひとりずつ解説します。
横山大観(よこやまたいかん)
横山大観は、いわずと知れた日本画の巨匠です。
輪郭線を描かずに対象の輪郭をぼかして表現する「朦朧体(もうろうたい)」を確立した画家で、日本だけでなく海外でも高く評価されています。
日本画では常識であった墨の線を用いない技法は、はっきりとしない印象が受け入れられず、批判的な意味を込めて朦朧体と呼ばれました。
日本で朦朧体が拒絶されたため、海外に目を向けた横山は、アメリカやインドでの展覧会を開催します。海外で賞賛された大観の作品は日本に逆輸入される形で、国内でも認められていきました。
中国の政治家・詩人をモチーフにした「屈原(くつげん)」や、全長40mの超大作「生々流転(せいせいるてん)」が代表作です。
菱田春草(ひしだしゅんそう)
菱田春草は、横山大観や下村観山と並ぶ、明治時代の巨匠です。インドやアメリカ、ヨーロッパに渡って知識・技術を学び、穏やかな色彩と繊細さが魅力の作品を多く残しています。
輪郭線を描かない朦朧体を試み、世間に批判されたこともありましたが、不屈の精神と芸術への探究心で美しい作品を作り上げました。
36歳の若さでこの世を去った巨匠の作品は、今なお多くの人に愛されています。
代表作に、雑木林に落ちる枯葉を遠近法で表現した「落葉」や、美しい構図と猫の毛並みを表現した「黒き猫」があります。
竹内栖鳳(たけうちせいほう)
近代日本画の祖といわれる竹内栖鳳は、日本の美しい四季を捉えた景色や動物画などを描いた有名画家です。
評価の高さは日本だけにとどまりません。1900年に開催されたパリ万博では、雪景色と雀を描いた「雪中躁雀図(せっちゅうそうじゃくず)」が銀牌を受賞し世界に名を轟かせました。
1937年には数々の功績が認められ、横山大観と並んで文化勲章を受賞します。東の横山大観、西の竹内栖鳳と賞賛されるほどの実力者です。
代表作にローマの廃墟を日本画で表した「羅馬之図(ろうまのず)」や、重要文化財に指定されている「班猫」があります。
下村観山(しもむらかんざん)
下村観山は、1889年に東京美術学校(現・東京藝術大学)の1期生として入学します。同学の横山大観や菱田春草とともに切磋琢磨し、卒業後は助教授として後進の育成にも携わりました。
下村の作品は動物や風景だけでなく、宗教や歴史上の人物などをモチーフにしたものがあります。
ストーリー性を感じさせる作風と今に動き出しそうな人物描写が魅力で、世界的に評価される作品を残しました。
代表作に釈迦が荼毘に付されるさまを描いた「闍維(じゃい)」や、能の演目の一場面を切り取った「弱法師」があります。
上村松園(うえむらしょうえん)
上村松園は日本女性の美しさを描いた京都生まれの女流画家で、気品ある美人画を女性の視点で描きました。
明治時代において女性が画家を目指すのは難しいことでしたが、女手一つで松園を育て上げた母のサポートもあり日本画家としての地位を確立したのです。
1948年には、女性として初めて文化勲章を受賞。
清少納言や楊貴妃など古典文学から着想を得た作品を作り、プライベートでは未婚の母として力強く生きた女性です。
代表作に、能をモチーフにした「焔(ほのお)」や、息子の嫁をモデルにした作品「序の舞(じょのまい)」があります。
大正の有名な日本人画家

大正時代の有名画家として以下の5人を紹介します。
- ・竹久夢二(たけひさゆめじ)
- ・梅原龍三郎(うめはらりゅうざぶろう)
- ・安井曾太郎(やすいそうたろう)
- ・吉田卓(よしだたかし)
- ・岸田劉生(きしだりゅうせい)
それぞれ見ていきましょう。
竹久夢二(たけひさゆめじ)
竹久夢二は1884年、岡山県生まれの大正時代を代表する詩人画家です。雑誌や新聞にコマ絵を送ることから画家として歩み出し、徐々に頭角を現します。
「夢二式美人」と称される情感あふれる美人画を確立し、瞬く間に人気作家となったのです。
絵画だけにとどまらず、雑誌の広告・うちわ・浴衣などの日用品のデザインを手がけ、ビジネスや出版業界でも卓越した才能を見せました。
代表作に、愛した女性・彦乃をモデルにした「黒船屋」、長崎の風景を描いた「長崎十二景」があります。
梅原龍三郎(うめはらりゅうざぶろう)
梅原龍三郎は日本を代表する京都生まれの洋画家です。1908年にフランスに渡り、フランス印象派の巨匠ルノワールに出会います。
作品に感動した龍三郎はルノワールを師と仰ぎ、芸術家としての技術を高めました。
ルノワールに強く影響を受けた画風は、華やかさと豪快さを兼ね備えた作品が多く、日本画と洋画が入り混じった日本の洋画を確立しました。
美しい色彩と力強い画風が特徴の富士山を描いた作品や、独特なタッチと生命力を感じさせる「薔薇」などが代表作として評価されています。
安井曾太郎(やすいそうたろう)
安井曾太郎は、梅原龍三郎と並んで賞賛された洋画家です。1888年に京都府で生まれた安井は、1904年に聖護院洋画研究所に入り、浅井忠に教えを受けます。
1907年にはフランスに渡り、ジャン・ポール・ローレンスを師として腕を磨き、ピサロやセザンヌの影響も受けました。
安井作品の魅力は、造形的な画面構造の組み立てにあり、モチーフとなる人物や場所に立体的な表現を与えました。
ゆったりと落ち着ついた女性を描いた「金蓉(きんよう)」や、女性が足を洗う姿を重厚に表現した「足を洗う女」などが代表作です。
吉田卓(よしだたかし)
吉田卓は1897年、現在の広島県福山市に生まれ、1920年に川端画学校本郷洋画研究所に入って学びを深めました。
二科展を主催する美術団体「二科会」で活躍し、大正期の最新の美術を伝えた画家のひとりです。
1922年の第9回二科展に「椅子に凭る(もたれる)」で初入選すると、その後16回まで連続で出品しました。
1926年の第13回二科展では、「羽扇を持てる裸婦」で二科会の最高賞である二科賞を受賞しています。
初期の緻密な描写にはじまり、堅実さが際立つ写実、幻想的画風など、多様な作品を残しています。
岸田劉生(きしだりゅうせい)
岸田劉生は大正から昭和に活躍した才能豊かな洋画家です。
同時期に活躍した画家の多くがフランス・パリの芸術に影響されるなか、岸田は日本の浮世絵や北方ルネサンス、中国の古典美術などに注目したことで、孤高・個性的と評価されます。
写実を通して対象の持つ神秘的な魅力を引き出すことを狙った手法や、東洋の美術が持つ独特な美に影響された作品を多く残しました。
ほくろやしみなど細部まで再現した肖像画を、「岸田の首狩り」「千人斬り」と揶揄されるほど、多く製作しています。また、愛娘である麗子をモデルにした「麗子像」シリーズも有名です。
1921年に発表した「麗子微笑」は切手のデザインにも採用されています。
昭和の有名な日本人画家

昭和の有名画家として、以下の5人を紹介します。
- ・東山魁夷(ひがしやまかいい)
- ・杉山寧(すぎやまやすし)
- ・髙山辰雄(たかやまたつお)
- ・小磯良平(こいそりょうへい)
- ・東郷青児(とうごうせいじ)
それぞれ見ていきましょう。
東山魁夷(ひがしやまかいい)
東山魁夷は、日本の風景画を極めた昭和を代表する日本画家です。
静寂と透明感に満ちた風景表現が特徴で、日本全土や中国・ヨーロッパへの旅を通して、自然と調和した美しさを追求した作品を残しています。
杉山寧・高山辰雄と並んで「日本画三山」と呼ばれ、戦後の日本において日本画の発展に尽力しました。
代表作に自然の美しさと静けさを表現した「緑響く」や、森にただずむ白馬を描いた「白馬の森」などがあり、神秘的な世界に引き込まれるような魅力があります。
杉山寧(すぎやまやすし)
杉山寧は、精緻な描写と独自の色彩感覚を持つ日本画家です。
デッサン力に優れ、日本画では描かれることのなかったピラミッドや古代遺跡、ギリシャ神話を題材にした作品などを手がけ、日本画に新風を起こしました。
杉山寧の作品の魅力は写実性と構成力です。対象物を鋭い観察力で写実的に捉えるだけでなく、構図や画面構成を工夫して魅力を引き出すように表現されています。
写実表現と抽象表現をミックスさせた二重構造の作風は「造形主義」と呼ばれ、高く評価されています。
巨牛に腰かけた裸婦を描いた「エウロペ」や、大きく羽を広げた孔雀を描いた「孔雀」などが代表作です。
高山辰雄(たかやまたつお)
高山辰雄は1912年に大分県で生まれた日本画家です。
東山魁夷・杉山寧とともに「日本画三山」と称され、日本画に革新を起こした画家であり、文化勲章も受賞しています。
人物や自然をモチーフにして、生命力と愛情を豊かな色彩で幻想的に表現した作品を多く残しています。
1946年の第2回日展では「裸婦」で特選をとり、1949年に「少女」でも特選を得た高山は、独自の芸術を発展させていきました。
1990年発表の、遠くを見つめる女性の横顔を描いた「椅子に」は、美しさと人間の闇を捉えた代表作です。
小磯良平(こいそりょうへい)
小磯良平は日本の洋画界を代表する画家のひとりで、優雅で洗練された人物画を数多く残しています。
東京芸術学校を首席で卒業した小磯は、詩人の竹中郁とともにヨーロッパに渡り、西洋の芸術に多大な影響を受けました。
手がけた作品は、西洋美術の技法を取り入れながらも、日本人ならではの繊細な感覚が息づいています。
代表作「斉唱」では、楽譜を手に裸足で歌う女性の姿を柔らかく優美に描いています。
東郷青児(とうごうせいじ)
東郷青児は、独自のロマンチックな作風で知られる洋画家です。
柔らかな曲線と淡い色彩が特徴的に用いられ、女性の美しさを幻想的に表現しています。「青児美人」と呼ばれる独特の女性像は、雑誌や包装紙など絵画以外にも使用され、昭和の美人画家として一生を風靡しました。
ギリシャの遺跡のような建物の前にただずむ女性を描いた「望郷(ぼうきょう)」は、1959年の第5回日本国際美術展で大衆賞を受賞しています。
独特のエレガントな世界観は、多くのファンに愛されています。
日本の現代アートも魅力あり|時代を牽引する芸術家5選

現代アートとは、戦後1950年以降に製作された作品で、美術概念にとらわれない前衛的な作品のことです。
日本画や洋画と比較してアグレッシブな作品が多く、アート初心者でも楽しめる作品が多くあります。
ここでは、現代アートの巨匠を5人紹介します。
- ・草間彌生(くさまやよい)
- ・岡本太郎(おかもとたろう)
- ・村上隆(むらかみたかし)
- ・奈良美智(ならよしとも)
- ・横尾忠則(よこおただのり)
それぞれ見ていきましょう。
草間彌生(くさまやよい)
草間彌生は、日本を代表する前衛芸術家であり、世界的に最も影響力のあるアーティストのひとりです。
彼女の作品は、トレードマークである水玉模様(ポルカドット)や反復するパターンが特徴で、絵画・彫刻・インスタレーション・パフォーマンスアートなど多岐にわたる表現を行っています。
代表作「南瓜(かぼちゃ)」は、黄色と黒の水玉で覆われた巨大なカボチャのオブジェで、香川県の直島で展示されていることで有名です。
無限に広がる鏡の部屋「インフィニティ・ミラー・ルーム」も、没入型アート作品として世界中で大きな反響を呼んでいます。
「芸術で世界を救う」という信念のもと創作を続ける草間彌生の作品は、多くの人々に希望を与えています。
岡本太郎(おかもとたろう)
「芸術は爆発だ」の名言で知られる岡本太郎は、日本の現代美術に大きな影響を与えた芸術家です。
岡本の特徴は、無機と有機・動と静・美しさと醜さなど矛盾する2つを対比した対極主義です。
1949年発表の「重工業」では農産物と工業、生命と巨大な機械といった、相対する両者がぶつかりあうさまを描いています。
また、戦争体験も作品に影響を与え、戦争で生じる怒りや抵抗を激しく表現した「明日の神話」は、戦争の悲惨さや怖さを感じさせる作品です。
圧倒的なエネルギーと独特の造形美によって、多くの人々に衝撃を与え続けています。
村上隆(むらかみたかし)
村上隆は、現代アートとポップカルチャーを融合させた「スーパーフラット」理論を提唱し、世界的に高い評価を受ける芸術家です。
アートに詳しくなくても村上隆の名や作風は知っている方も多いでしょう。
可愛らしい笑顔を浮かべるカラフルな花のモチーフが有名で、ルイ・ヴィトンやユニクロなど一流企業とのコラボも行っており、芸術家としてだけでなくビジネスにおいても高い評価を受けています。
日本のサブカルチャーを芸術に昇華させた第一人者です。
代表をつとめるアートの総合商社「カイカイキキ」では、自身の創作だけでなく後進育成にも注力しています。
奈良美智(ならよしとも)
奈良美智は、無垢な表情の中に強い意志を秘めた少女の絵で知られる画家・彫刻家です。
彼の作品には、可愛らしさの中に、どこか孤独や不満を感じさせるような表現があり、見る者の心を揺さぶります。
代表作「睨みつける少女」シリーズは、世界の舞台で知られるきっかけとなり、1990年後半のニューヨークでの展覧会で広く注目を集めました。
2000年に制作した「Knife Behind Back(ナイフ・ビハインド・バック:背中にナイフを隠す子ども)」は、2019年のサザビーズ香港のオークションで約27億円という驚異的な金額で落札されました。
国内外で展覧会が開催されるたびに多くの観客を動員し、現代アートの枠を超えて広い支持を集める芸術家のひとりです。
横尾忠則(よこおただのり)
横尾忠則は1936年、兵庫県生まれの日本を代表するグラフィックデザイナー・画家です。
1960年代からポップアートの影響を受け、日本の伝統的なモチーフと組み合わせた大胆なビジュアルスタイルを確立しました。
1980年にニューヨーク近代美術館で開催されたピカソ展で衝撃を受けた彼は画家に転身。
滝や洞窟といった自然の風景、街中にある「Y字路」を表現したシリーズ、俳優やミュージシャンなど時代を彩るスターを描いた肖像画などさまざまな作品を生み出しています。
2023年には芸術や文化の発展への功績が認められ、文化功労者に選出されています。
参考:日本経済新聞|文化勲章・文化功労者の業績 2023年度
絵画の価値を決めるポイント

絵画の価値は市場での需要や歴史的背景、保存状態など、さまざまな要素が絡み合い、最終的な評価が決まります。
ここでは絵画の価値を決める主なポイントとして、以下の3つを紹介します。
- ・作者の知名度
- ・希少性が高い
- ・状態が良い
ひとつずつ確認していきましょう。
作者の知名度
絵画の価値を決定づける重要な要素のひとつが、作者の知名度です。有名画家の作品は、美術市場で高く評価され、投資対象としての価値も高まります。
日本画家の巨匠である横山大観や東山魁夷、現在アートの草間彌生・奈良美智といった有名芸術家の作品は、国内外で高い人気を誇ります。
オークションで数千万円という高額で落札される作品もあり、画家の知名度や影響力が大きいほど、その作品の市場価値も上昇しやすい傾向です。
希少性が高い
希少性の高さも絵画の価値を決めるポイントです。例えば、岩絵具などで作られた作品や、水墨画は1点ものが多く、希少性が高く評価されます。一方で、複数枚刷られる版画作品などは希少性が上がりにくい傾向です。
戦争や災害で消失したとされる作品が偶然見つかった場合など、希少性が跳ね上がるケースがあります。
未発表の作品や初期に制作した作品がオークションに出品されて、高額で落札される場合もあります。
状態が良い
絵画の状態も価値を左右するポイントです。絵画は、管理の仕方や経年劣化によって絵画の表面がぱっくりと割れたり、カビやシミが発生したりします。
古い作品にもかかわらず保存状態の良い絵画には高い価値が認められます。
ただし、自己流で修復したり、擦って汚れを落とそうとしたりすると、かえって絵画の価値を下げる可能性があるため控えたほうがよいでしょう。
なお、絵画の買取における注意点を知りたい方は、こちらの記事も参考になります。
有名な日本人画家のアートの価値

有名画家のアートにどれだけの価値があるのか、以下の3人の作品を例に挙げて紹介します。
- ・横山大観作品の価値
- ・草間彌生作品の価値
- ・奈良美智作品の価値
それぞれ見ていきましょう。
なお、紹介する作品の価格は、一般的な相場であり『買取むすび』での買取額を約束するものではありません。
横山大観作品の価値
日本の巨匠である横山大観は、富士山や海・雲海などの風景を題材にした作品を多く残しました。
特に富士山の絵画は独特の色彩感覚と繊細さで優雅に描いており、高い価値が認められています。
富士山を描いた作品なら、500万円以上の価値が認められることがあり、作品によっては2,500万円を超えるケースもあります。
掛け軸でさらりと描いた作品でも100万円以上の金額がつく場合もあるのです。
一方で、版画や複製画の場合は、1万円以下で取引されることがあり、横山大観の作品ならどれも高額というわけではありません。
草間彌生作品の価値
世界で活躍する現代アートの巨匠、草間彌生はこれまで多くの作品を生み出しており、公開オークションに出品されてた作品は1万点にもおよびます。
作品の価値は、技法や絵柄によって異なり、アクリル画は1,000万円以上で取引され、ときに5億円を超えることもあります。
網目のような模様が張り巡らされた「Untitled (Nets)」は、2022年にニューヨークで開催されたオークションにおいて日本円にして13億5,000万円で落札されました。
鑑定によって本物と証明された作品や、シミやカビのない状態が良い作品は高額で取引される可能性が高まります。
奈良美智作品の価値
現在アート作家として知名度のある奈良美智の作品は、国内外で高く評価されています。
美術品オークションに初出品された「一人じゃない。」は、オークションハウス・サザビーズの香港オークションで、35点の所蔵物が合計で5億1,496万円もの高額で落札されました。
2015年には「Yr. Childhood」が3億円を超える落札額を記録するなど、億超えの作品が多数見られます。
ネットオークションでも奈良美智の絵画やぬいぐるみなどのグッズが多く出品されており、数十万円から100万円を超えて落札される場合もあります。
絵画を鑑賞するときの楽しみ方

絵画を楽しむ方法は人それぞれですが、いくつかのポイントを押さえると、より深く作品を味わえます。
具体的な楽しみ方は、以下のとおりです。
- ・直感的に作品を感じる
- ・作者の経歴を調べる
- ・作品の背景を理解する
- ・構図や技法を楽しむ
色彩や構図、筆使いなど、作品の第一印象を直感的に感じることで、自分だけの解釈が生まれます。そのうえで、作者の経歴や作品に込められた意図や背景を知ると、作品の良さをより深く理解できます。
絵画の鑑賞に慣れてきたら、構図や技法を調べ、異なる時代や流派ごとの特徴を意識してみるのもおすすめです。
自分なりの視点を持ち、自由に芸術の世界を楽しみましょう。
絵画の価値を知りたい方は『買取むすび』の無料査定がおすすめ

絵画の価値は作者の知名度や作品の状態によって異なり、有名作家の作品は高い価値がつく場合があります。
『買取むすび』は骨董品や美術品の買取実績が豊富です。不要な美術品を買取に出し、絵画やアート作品の購入資金に充ててみてはいかがでしょうか。
以下のボタンから『買取むすび』の骨董品買取ページを確認できます。