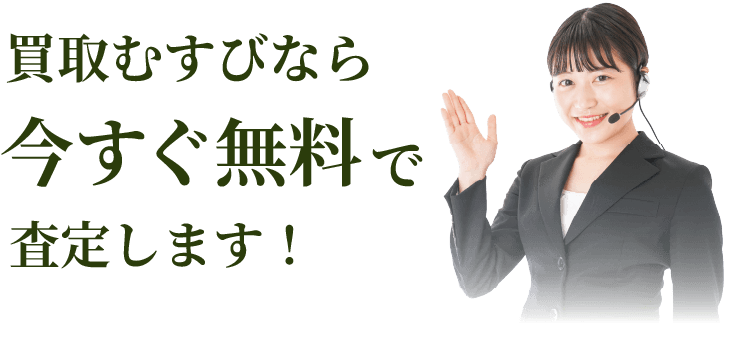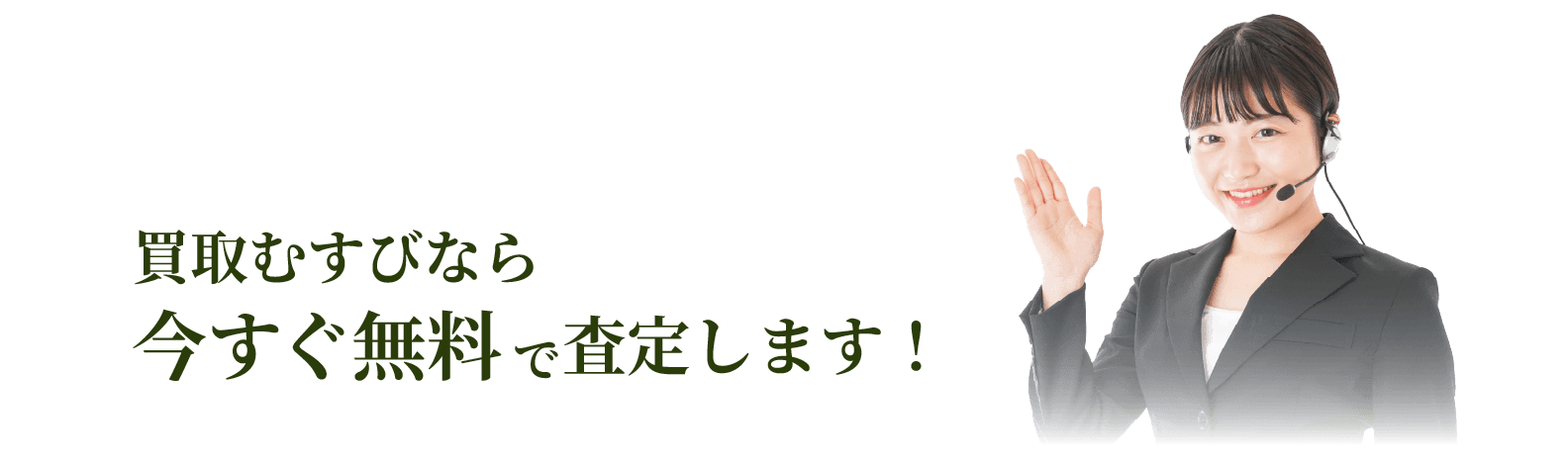執筆:
買取むすび 編集部
日本茶・抹茶・中国茶の茶器の種類を解説|使わないものは『買取むすび』が高価買取

「茶器の種類が知りたい」
「どれが何なのか分からない」
このように考えていませんか?
お茶を飲む文化は今から4500年以上前からあったといわれています。日本でも奈良時代にお茶文化が伝えられたとされており、今では誰もが日常的に口にする飲み物となっています。
今でこそ簡単に購入でき作れるお茶ですが、ひと昔前までは茶器を使って入れる必要がありました。そのため、家を掃除していたら親族が使っていた茶器が出てくることも珍しくありません。
しかし、どれが何という名称なのか、何に使うのかわからない方もいるでしょう。この記事では、茶器の種類について日本茶・抹茶・中国茶の3つにわけて解説します。ぜひ参考にしてみてください。
目次
日本茶|茶器の種類

日本茶が飲まれるようになったのは奈良から平安時代です。日本茶のルーツは中国にありますが、長い時間をかけて製法や風味が変わり、現在に至ります。そのため、日本の茶器は中国の茶器と似ている役割のものが多い傾向があります。
日本茶の主な茶器は以下のとおりです。
- ・茶碗
- ・茶たく
- ・急須
- ・茶筒
- ・茶さじ
- ・絞り出し
- ・湯冷まし
どのような役割があるのか、ひとつずつ解説します。
茶碗
茶碗は、日本茶を飲むときに使われる器です。茶碗というと、白米を盛る器をイメージするかもしれませんが、名前からわかるとおり「お茶を飲むための碗(飲食物を入れる器)」であり、本来は茶道具として使われていました。
白米を盛る器も茶碗といわれているため、茶器の茶碗は「湯呑み茶碗」と呼ばれています。多くの家庭にひとつは置かれている日本人にとって馴染みのある器です。
茶たく
茶たくは、茶碗の下に敷く茶器です。茶器の滑り止めや、テーブルにキズつくのを防ぐために使われており、コースターと同じ役割があります。
お茶を入れるのに必須アイテムではないため、あまり使われないかもしれません。来客や冠婚葬祭などの場面でおもてなしアイテムとして多く使われています。
急須
急須は茶葉からお茶を煮出し、茶碗に注ぐ茶器です。ひょっとこの口に似た形の注ぎ口と、90度の位置に持ち手があるのが特徴で、誰もが一度は目にしたことがあるでしょう。
急須の中には、取り外し可能な「かご網」が付属している場合があります。しかし、かご網があると中に閉じ込められた茶葉がお湯とうまく対流できず、お茶が抽出されにくくなるため、お茶の味を存分に楽しめません。
お茶をおいしく飲むためには、取り外しできない網がつけられたものや、注ぎ口に網目のように穴が開いている「ささめ」が施された急須がおすすめです。
茶筒
茶筒は、茶葉を保管するための容器です。茶葉は空気に触れると酸化し、徐々に味が損なわれます。そのため、茶筒は本体とフタの間が非常に小さく作られており、密閉性に優れているのが特徴です。
茶葉の品質は味に大きく影響するため、おいしくお茶を飲むためには欠かせないアイテムといえるでしょう。
茶さじ
茶さじは、茶筒から急須に茶葉を移す際に使われるお茶専用のさじです。容量は5ml前後サイズが主流で、一般的なテーブルスプーンより小さめに作られています。
茶さじのほかにも、茶量(ちゃりょう)・茶計(ちゃけい)・茶合(ちゃごう)とも呼ばれている茶器です。
絞り出し
絞り出しはフタ付きの茶碗のような見た目ですが、小さな注ぎ口が付いています。急須と同様に中に茶葉を入れて煮出し、茶碗に注ぐ茶器です。煎茶・玉露などの茶葉を楽しむ際に多く使われます。
湯冷まし
湯冷ましはお茶入れに使うお湯を冷ますための茶器です。日本茶の中には、煎茶や玉露など60~80℃と比較的低温で入れた方が美味しくなる茶葉があります。
沸騰したお湯を湯冷ましに注ぎ、容器に1度移しかえるごとに湯音が10℃下がります。
抹茶|茶器の種類
 抹茶は、碾茶(てんちゃ)と呼ばれる、揉まずに乾燥させた茶葉を臼で挽いて粉状にしたものです。抹茶も平安時代頃から飲まれていたとされており、現代でも茶道として入れ方が引き継がれています。
抹茶は、碾茶(てんちゃ)と呼ばれる、揉まずに乾燥させた茶葉を臼で挽いて粉状にしたものです。抹茶も平安時代頃から飲まれていたとされており、現代でも茶道として入れ方が引き継がれています。
厳密には抹茶も日本茶に部類されますが、茶器が異なるため、先ほど紹介した「日本茶|茶器の種類」とは別で紹介します。抹茶の茶器の種類は以下のとおりです。
- ・抹茶碗
- ・茶せん
- ・なつめ
- ・茶さじ
- ・懐紙(かいし)
ひとつずつ見てみましょう。
抹茶碗
抹茶碗は、名前のとおり抹茶を入れるための器です。茶碗の中で抹茶を点てるため、湯呑み茶碗とは異なり、直径10cm前後と口が広い特徴があります。
薄茶用のものと濃茶用のものなど、お茶の入れ方によって器が違うほか、冷めやすいように口が広い春~秋用の器があるなど、季節によっても使う器が異なるのも特徴です。
茶せん
茶せんは、抹茶を点てるための茶器です。多くの茶せんは竹でできており、調理器具の泡だて器のような形をしています。
先端部部は「穂先」と呼ばれており、入れ方や抹茶碗の種類によって穂先の本数を変える必要があるのも茶せんの特徴です。
なつめ
抹茶を保存するための容器です。抹茶は日本茶と同様、空気に触れると味が変化します。そのため、密閉性に優れた構造に作られているなつめは、美味しい抹茶を飲むのに欠かせないアイテムです。
茶さじ
茶さじは、なつめから抹茶碗に抹茶を移すための茶器です。茶さじのサイズはいくつもあり、お茶の相手や人数によって使い分ける必要があります。
例えば、お茶の相手が大勢いる場合は、待たせる時間を少なくスムーズに点てるために大き目のものを使うなどです。
茶人の人柄や価値観を表すアイテムとして重要視されている茶器でもあります。
懐紙(かいし)
懐紙は「ふところがみ」とも呼ばれている紙です。茶菓子を乗せる皿・箸・つまようじを拭き取るのに使われています。
普段から着物を着ていた時代には懐紙を持ち歩き、汚れを拭き取ったり、メモを取ったりとさまざまな用途に使われていました。
現代ではハンカチやティッシュペーパー・メモ帳などが主流となったため、懐紙は一般的に使われなくなりました。
中国茶|茶器の種類

中国はお茶の発祥地といわれており、長くお茶を楽しむ文化を育んできた国です。そのため、中国茶の種類は多岐にわたり、数百にも及ぶといわれています。
中国茶は歴史が長いため、特殊な入れ方が必要だと思うかもしれませんが、多くの場合は日本茶と同様です。中国茶を入れるための茶器は名前こそ違いますが、役割に大きな違いはありません。
- ・茶壷(ちゃふう)
- ・蓋椀(がいわん)
- ・茶海(ちゃかい)
- ・茶杯(ちゃはい)
- ・聞香杯(もんこうはい)
- ・茶船(ちゃせん)
- ・茶罐(ちゃかん)
ひとつずつ見てみましょう。
茶壷(ちゃふう)
茶壷は、注ぎ口・フタ・取っ手が付いている器です。急須と同じ役割があり、中に茶葉を入れて煮出すのに使われます。
中国茶は香りが大切なため日本茶とは異なり、飲む分だけ入れるのが主流です。そのため、急須と異なり、小さめサイズの茶壺も多く流通しています。
蓋椀(がいわん)
蓋椀は、湯呑み茶碗と同じ役割のある器です。湯呑み茶碗と同じように、煮出したお茶を注ぎ入れます。また、蓋椀に茶葉を直接入れてに出し、フタをずらした隙間から飲むのも一般的です。
そのため、湯呑み茶碗と異なり必ずフタが付属しています。
茶海(ちゃかい)
茶海は、茶壷でにだしたお茶の香りや味を均一にするために使われる茶器です。複数人でお茶を入れる場合、順番に注げば最初の人は薄く、徐々に濃くなってしまうため、一度茶海に注ぎ入れて香りや味を均一にします。
ほかにも、日本茶の湯冷ましのように、使用するお湯を冷ますためにも使われています。
茶杯(ちゃはい)
茶杯は、お茶を飲むための茶器です。日本でいう湯呑み茶碗に該当します。お茶を飲む道具である蓋椀(がいわん)と異なるのは、フタが付属していない点です。
聞香杯(もんこうはい)
聞香杯は、お茶の香りを楽しむための茶器で縦長の形をしているのが特徴です。煮出したお茶を聞香杯に入れてから、茶杯(ちゃはい)に移し入れます。
聞香杯に残ったお茶の香りを楽しむための道具であり、日本にはない茶器です。
茶船(ちゃせん)
茶船は、茶壷(ちゃふう)・蓋椀(がいわん)・茶海(ちゃかい)・茶杯(ちゃはい)などを乗せる器です。お茶は器の温度が低いと味が落ちてしまいます。
そのため、中国茶ははじめに、フタの閉まっている茶壷(ちゃふう)にお湯をかけて器ごと温める工程があるのです。かけたお湯がテーブルにこぼれないように受け止めるために茶船が使われています。
似た役割の茶器として茶盤(ちゃばん)も一般的です。茶番は上面がすのこ状になっており、茶船と同様にかけたお湯を受け止める役割があります。大きいサイズの茶盤は茶器を一式仕舞えるなど、収納として使われる場合もあります。
茶罐(ちゃかん)
茶罐は、茶葉を保管する茶器です。茶筒やなつめと同じ役割があり、磁器・陶器・金属で作られたものも流通しています。
茶器に使われる素材

茶器には以下のようにさまざまな素材が使われています。
- ・磁器
- ・陶器
- ・鉄器
- ・ガラス
それぞれの特徴や魅力を紹介します。
磁器
磁器は、陶石(とうせき)と呼ばれる石を材料に作られる器です。吸水性が無い特徴から、使いまわしてもほかのお茶の香りが移りません。
長く使っても、お茶本来の香りを楽しめるのが磁器の魅力です。また、多くの磁器は薄く作られており、熱が伝わりやすい特徴もあります。そのため、低温で楽しむ煎茶や玉露などの茶葉と相性がよいでしょう。
陶器
陶器は、陶土(とうど)と呼ばれる粘度を材料に作られる器です。高い保湿性が特徴であり、一度にたくさんのお茶を作っても冷めにくい点が魅力に挙げられます。
ただし、吸水性が高い特徴もあり、水気をしっかり取り除かずに保管すればカビが発生する可能性がある点に注意が必要です。
磁器と陶器の違いについては以下の記事でより詳しく解説しています。
鉄器
鉄器も茶器の素材として有名です。鉄器の一番のメリットは耐久性の高さです。金属でできているため、磁器や陶器とは異なり落としたりぶつけたりしても簡単に割れません。
そのため、一生ものの茶器として愛用する人もいます。ただし、金属製の茶器は正しくお手入れしなければ劣化する可能性もあります。金属の種類によっては、劣化度合でお茶の味が変化する場合もあるため定期的なお手入れが欠かません。
ガラス
ガラス製の茶器は清涼感があり、夏に出す冷えた煎茶などを飲むのに向いています。耐熱性能のあるガラス容器もあるため、茶葉がお湯によって対流している様子を観察できるのも魅力のひとつです。
『買取むすび』は茶器を高価買取中

使う予定のない茶器は『買取むすび』が買取いたします。茶器は日常的に使われる道具で安く手に入れられますが、中には楽焼・萩焼・唐津焼など、作られた場所によっては高値が付く可能性があります。
茶器は種類が多いうえに、形が似ている物も多く、どれがどの茶器か分からなくなる場合もあるでしょう。しかし、種類や作られた場所がわからなくても問題ありません。
『買取むすび』は豊富な買取実績があり、茶器をはじめとした骨董品に精通した鑑定士が在籍しているため、価値のある茶器を見分けられます。
査定料は無料のため、ぜひお気軽に試してみてください。
茶器は種類がたくさんある|使わないものは買取に出すのがおすすめ

茶器は種類が多く、どれが何に該当するのか分からない場合もあるでしょう。
不要な茶器があれば、ぜひ『買取むすび』にご相談ください。価値のあるものは高価買取いたします。査定料は無料のため、ぜひお気軽におためしください。