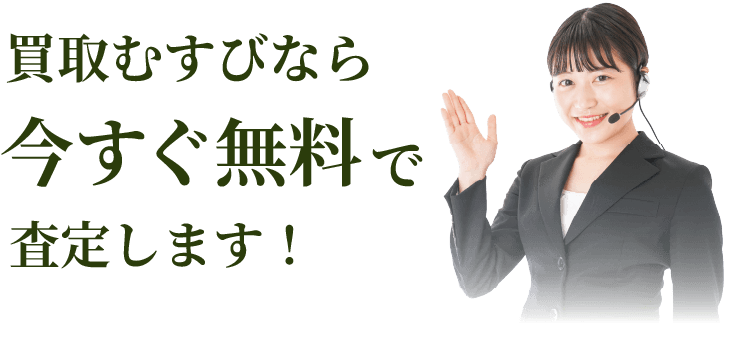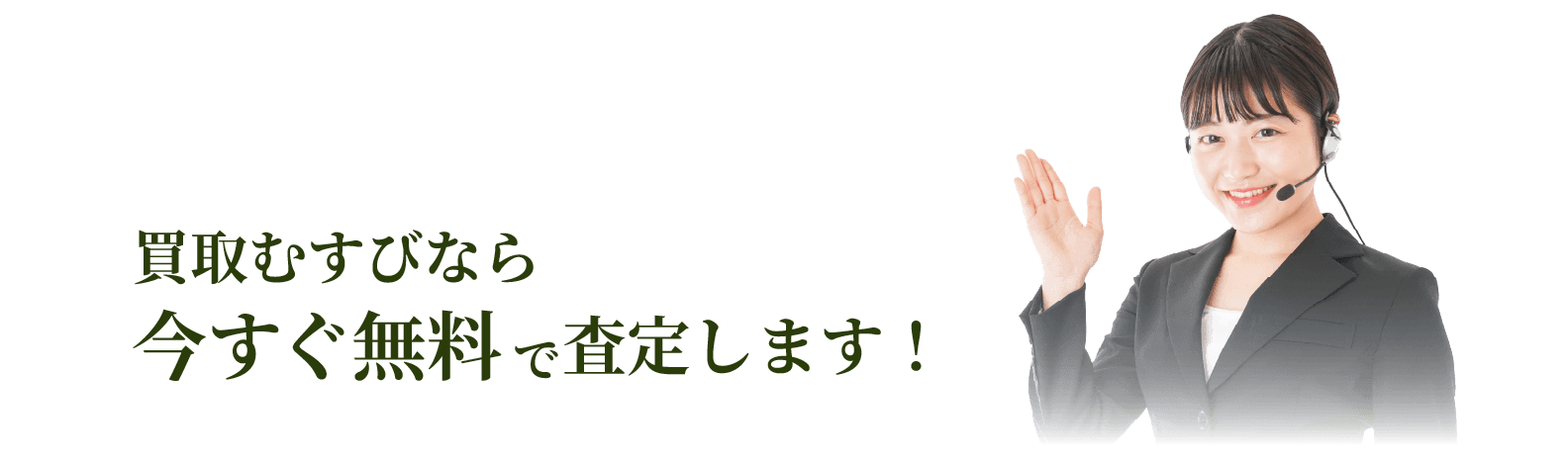執筆:
買取むすび 編集部
仏具とは?種類や使い方・役割を解説|高価買取となる仏具も紹介

「仏具って具体的に何を指す?」
「仏具の役割や使い方を知りたい」
このような疑問はありませんか?
仏具とは、仏教で使用される道具です。宗派によって用意する仏具が違ったり、それぞれ役割を持っていたりと、細かなマナーが存在します。
使い方を間違えると、ご先祖様や本尊に失礼にあたる可能性もあるため、使い方のマナーは知っておいて損はありません。
本記事では、仏具の使い方や役割・不要になった際の処分方法・高く売れる仏具の特徴を解説します。
仏具について知りたい方は、ぜひ参考にしてみてください。
目次
仏具とは?

仏具とは、仏様を祀る際に用いられる道具の総称です。ご飯・お茶・花・果物などをお供えするための器や、お経を読むための道具などが含まれます。
宗派によって使用する仏具の種類は異なりますが、共通して仏様への供養の心を表すものです。
素材には、貴金属・陶器・木などが用いられ、現代ではクリスタルなども使用されています。
本章では、仏具に関する基本的な以下の3点を解説します。
- ・仏具が普及したのは江戸時代
- ・仏具を飾り立てることを「荘厳」と言う
- ・仏具と神具の違い
上記の3点を把握すれば、より仏具への理解が深まるでしょう。
仏具が普及したのは江戸時代
仏具が普及したのは、江戸時代頃と言われています。
元々はお寺で僧侶が使用する道具でしたが、江戸時代になると仏壇が一般家庭に普及し、それに伴い仏具も広く使われるようになりました。
現在でも仏具は、家庭での供養に欠かせない存在として大切に利用されています。
仏具を飾り立てることを「荘厳」と言う
仏具を美しく飾り立てることを「荘厳(そうごん)」と言います。荘厳されたお仏壇は極楽浄土を表現し、仏様への敬意を示すものとされています。
荘厳の考え方は、どの宗派においても共通です。「信は荘厳より生ず」という言葉があるように、仏具を飾り立てるのは、信仰心を深めるうえで大切な行為のひとつとされています。
仏具と神具の違い
仏具と似ている道具に「神具(しんぐ)」があります。
神具は神道で用いられる道具で、神棚に供えられます。仏教よりも古くからある日本独自の宗教であり、自然や祖先を崇拝する点が特徴です。
神具の具体的な種類は、以下のとおりです。
- ・注連縄(しめなわ)
- ・三方(さんぼう)
- ・瓶子(へいじ)
- ・水玉(みずたま)
- ・御神鏡(ごしんきょう)
- ・榊立(さかきたて)
仏具は金を使用した煌びやかなものが多いのに対し、神具は白木や陶器などシンプルなものが多い傾向です。
仏具の種類

仏具は、大きく3つに分類できます。
- ・お参りの対象となる仏具
- ・必要な最低限の仏具
- ・その他の仏具
それぞれの種類や使い方を見ていきましょう。
お参りの対象となる仏具
お参りの対象になる仏具には、以下の3点が含まれます。
- ・本尊:信仰の対象
- ・脇仏:各宗派の開祖
- ・位牌:故人の魂が宿るもの
それぞれの役割やお仏壇での飾り方を解説します。
本尊:信仰の対象
本尊(ほんぞん)とは、仏教宗派で信仰の対象となる仏様を表したものです。宗派によって本尊の種類は異なります。
-
仏教宗派における本尊の違い
宗派
本尊
天台宗・浄土宗・浄土真宗
(大谷派・本願寺派)
阿弥陀如来(あみだにょらい)
真言宗
大日如来(だいにちにょらい)
臨済宗・曹洞宗
釈迦牟尼仏(しゃかむにぶつ)
日蓮宗・法華宗
十界曼荼羅(じっかいまんだら)
融通念仏宗
十一尊天得如来
(じゅういっそんてんとくにょらい)
仏壇の中心に安置される重要な仏具のひとつで、仏像と掛け軸の2つのタイプがあります。
仏像は立体的な仏様の姿を表しており、掛け軸は仏様の絵画を巻いたものです。
脇仏:各宗派の開祖
脇仏(わきぶつ)は本尊の左右に配置される仏具です。各宗派の開祖や、仏教に影響を与えた僧侶を祀るために用意します。
本尊と同じように、宗派によって飾る脇仏が異なります。
仏教宗派における脇仏の違い
|
宗派 |
脇仏 |
|
天台宗 |
右:天台大師・智顗 左:伝教大師・最澄 |
|
真言宗 |
右:弘法大師 左:不動明王 |
|
浄土宗 |
右:高祖善導大師 左:法然上人 |
|
浄土真宗(本願寺派・大谷派) |
右:親鸞聖人 左:蓮如上人 |
|
臨済宗 |
右:達磨大師 左:観世音菩薩 |
|
曹洞宗 |
右:高祖道元禅師 左:太祖瑩山禅師 |
|
日蓮宗 |
右:鬼子母神 左:大黒天 |
|
法華宗 |
右:鬼子母神 左:日隆聖人 |
|
融通念仏宗 |
右:良忍上人 左:法明上人 |
※日本にはさまざまな分派があるため、脇仏が表と異なる場合があります。
位牌:故人の魂が宿るもの
位牌(いはい)は、亡くなった方の戒名や没年月日を書き入れたもので、故人の魂が宿ると考えられています。仏壇の右側に安置して供養の対象とします。
なお、浄土真宗では宗教上の教えにより、位牌の代わりに法名軸を使用します。
法名軸は、無地の掛け軸に故人の法名を書き入れたものです。
必要な最低限の仏具
仏壇に必要な最低限の仏具として、三具足(みつぐそく)や仏飯器、茶湯器などがあります。三具足とは、香炉・燭台・花立の3つの仏具を指します。
それぞれの役割は、以下のとおりです。
- ・香炉:お線香を焚くための器
- ・燭台:ろうそくを灯すための台
- ・花立:お花を生ける花瓶
- ・おりん:邪気を払うための鈴
- ・茶湯器:お水やお茶を供える湯呑み
- ・仏飯器:ご飯を供えるための器
なお、三具足の燭台と花立が対で2つずつある場合は「五具足(ごくそく)」と呼びます。
香炉:お線香を焚くための器
香炉(こうろ)は、本尊や故人のためにお線香を焚くための器です。なかに灰を入れ、お線香を灯します。
仏教では、線香の煙が故人の食べ物となり、またあの世とこの世をつなぐ役割を果たすとされているため、毎日欠かさず灯すのがよいとされています。
お線香を立てるか寝かせるかは、宗派によってさまざまです。
燭台:ろうそくを灯すための台
燭台(しょくだい)は、ろうそくを立てるための道具で「火立(ひたて)」とも呼ばれています。
仏教では、ろうそくの炎が世の中の真理を象徴し、仏様の智慧を表すものとされています。
供養するうえで欠かせない仏具のひとつです。
花立:お花を生ける花瓶
花立(はなたて)は、仏花を生けるための仏具です。仏花だけでなく、故人の好きだった花を供えてもよいとされています。
お仏壇にお花を供える理由は諸説ありますが「お釈迦様が修行中に仏様へのお供えとして花を買った」「仏様の慈悲と忍耐を表す」の2つが有力です。
おりん:邪気を払うための鈴
おりんは、お椀型の鈴で、お経を唱える際や手を合わせる際に使用します。りん・リン座布団・りん台・りん棒で1セットです。
おりんの音色には邪気を払う効果があるとされています。元々は禅宗のみに使用されていましたが、現在では宗派を問わず広く使われるようになりました。
宗派によって鏧(きん)・小鏧(しょうきん)・鐘(かね)と名称が異なる点が特徴です。
茶湯器:お水やお茶を供える湯呑み
茶湯器(ちゃとうき)は、お水やお茶を供えるための湯呑みです。
浄土真宗では「極楽浄土には水が満ちている」との考えから不要とされますが、供養の気持ちで供える場合もあります。
仏飯器:ご飯を供えるための器
仏飯器(ぶっぱんき)は、ご飯を供えるための仏具です。伝統的な形のものから現代的なデザインのものまで多くの種類があります。
ご飯は、その日の炊き立てを一番に供えるのがマナーとされています。
その他の仏具
必須ではないものの、持っていたほうがお参りや供養がしやすい仏具が、以下の12点です。
- ・過去帳:法名を記した帳面
- ・木魚:お経のテンポを整える楽器
- ・高杯:お菓子や果物を供えるための器
- ・線香立て:線香の予備を入れる道具
- ・火消し:ろうそくの火を消すための仏具
- ・吊り灯篭:仏壇を照らす照明器具
- ・瓔珞:仏壇をいろどる装飾品
- ・常花:極楽浄土に咲く花を模した飾り
- ・お仏壇マット:仏具の下に敷くマット
- ・経机:お経を読むための机
- ・霊供膳:精進料理用の器セット
- ・焼香炉:抹香を焚くための道具
それぞれの役割をみていきましょう。
過去帳:法名を記した帳面
過去帳(かこちょう)は、故人の法名や没年月日を記録する帳面です。見台と呼ばれる専用の台に置かれて使用されます。
家系図のような役割も果たしており、幅広い宗派で用いられます。特に浄土真宗では、位牌の代わりに過去帳を置く家庭もあるほどです。
木魚:お経のテンポを整える楽器
木魚(もくぎょ)は、読経のリズムを整えるための仏具です。
木魚が魚を模している理由は、目を瞑らない習性から「寝る間を惜しんで修行に励むように」という意味が込められていると言われています。
日蓮宗では木鉦(もくしょう)と呼ばれる円形の法具を使用し、真言宗や浄土真宗では使用しない場合もあります。
高杯:お菓子や果物を供えるための器
高杯(たかつき)は、お菓子や果物を供えるための仏具です。脚部が高い作りになっており、仏様を敬う気持ちを表しています。
また、果物の汁で仏壇が汚れるのを防ぐ役割も果たしています。日常の供養から法要まで、幅広く使用される仏具のひとつです。
線香立て:線香の予備を入れる道具
線香立ては、使用前の線香をストックしておくための仏具です。
「線香差し」とも呼ばれ、香炉とセットで仏壇に置かれるのが一般的です。
火消し:ろうそくの火を消すための仏具
火消しは、仏壇で使用するろうそくの火を安全に消すための仏具です。小さなうちわ型・帽子型・トング型などさまざまな形状があります。
火消しを使用すれば、火災のリスクを減少できます。ただし、火消しを持たない家庭も少なくありません。
吊り灯篭:仏壇を照らす照明器具
吊り灯篭(つりどうろう)は、仏壇を照らすための照明器具で、天井から吊り下げて使用します。
大きな仏壇に設置されており、コンパクトな上置き型仏壇では使用されるケースが少ない傾向です。
瓔珞:仏壇をいろどる装飾品
瓔珞(ようらく)は、仏壇を飾る装飾品で、2個セットで左右対称に飾ります。
起源は古代インドの王族の装身具にあり、仏教では菩薩像の首飾りや胸飾りとして用いられてきました。
なお、コンパクトな上置き型仏壇には、あまり使用されていません。
常花:極楽浄土に咲く花を模した飾り
常花(じょうか)は、金属製で作られた造花の仏具です。浄土に咲く蓮の花を模しており、極楽浄土を象徴しています。
ただし、浄土真宗では、生花をお供えするべきと考えられているため、お仏壇には浄花を飾りません。
お仏壇マット:仏具の下に敷くマット
お仏壇マットは、仏具の下に敷いて使用するマットです。
マッチ・ろうそく・線香の火による火災、お供物による汚れから仏壇を守るために使用されます。
経机:お経を読むための机
経机(きょうづくえ)は、読経の際に経本や経典を置くための仏具です。
「供物机(くもつづくえ)」とも呼ばれ、現在では香炉・花立・供物を置く場所としても使われています。
読経だけでなく、多目的に活用できる便利な仏具です。
霊供膳:精進料理用の器セット
霊供膳(れいぐぜん・りょうぐぜん)は、お彼岸やお盆などで供養のために用いられる精進料理用の器セットです。
ご飯や汁物などを盛る専用の器が一式揃っています。特別な供養のために用いる重要な仏具です。
なお、浄土真宗では宗教上の教えにより霊供膳を使用しません。
焼香炉:抹香を焚くための道具
焼香炉(しょうこうろ)は、抹香を焚くための仏具です。灰を入れた上に熱した炭を置き、その上から抹香を振り掛けます。
年忌法要を自宅で執り行う家庭は、ひとつ持っておくと便利です。
高く売れる仏具の特徴

仏具のなかには、高く売れる種類も存在します。高額査定が期待できる仏具の特徴は以下のとおりです。
- ・有名な職人が作った仏具
- ・金・銀・プラチナで作られている仏具
上記の特徴に該当する場合、思わぬ価値を持つ可能性があります。
有名な職人が作った仏具
有名な職人が作った仏具は、美術品としての価値を持つ場合があります。
特に細部まで精巧に作られた仏具は芸術品としての評価が高く、海外ではインテリア雑貨としても人気を集めています。
具体的な仏具の例は、以下のとおりです。
- ・仏像
- ・仏画
- ・花立
- ・曼荼羅
作られた時代や希少性によっても価値が変動する場合もあります。
金・銀・プラチナで作られている仏具
金・銀・プラチナなどで作られた仏具は、素材そのものに価値があるため、高額で取引される可能性があります。
貴金属が用いられている仏具の一例は、以下のとおりです。
- ・金仏壇
- ・仏像
- ・花立
- ・おりん
- ・燭台
貴金属の純度が高いほど買取価格が高額になる傾向です。
仏具を売却・処分する前にやっておくべきこと

仏具を売却・処分する際には、以下の3点に注意しましょう。
- ・祭祀継承者の理解を得ておく
- ・閉眼供養をしておく
- ・売る前にきれいにしておく
上記の3点に気を付けておけば、後々のトラブルを回避できる可能性があります。
祭祀継承者の理解を得ておく
仏具を売却・処分する際には、親族や祭祀継承者の理解を得ておくのが大切です。
仏具は通常の財産と異なり「祭祀財産」として扱われます。
祭祀財産は、親から子へ受け継がれるのではなく、故人が指定した祭祀を主宰する1人に相続される財産です。
一般的には親から子へ受け継がれますが、指定した人物が子以外の場合、知らずに売却・処分すると返還を求められる可能性があります。
そのため、仏具を処分する前には親族や祭祀継承者に確認を取り、理解を得ておくのが大切です。
閉眼供養をしておく
特定の仏具を処分する前には、閉眼供養をしなければなりません。閉眼供養とは、仏具に宿っている魂を抜く儀式です。
対象物は、仏像・掛軸・位牌の3つです。僧侶に依頼し、お布施を渡して閉眼供養を執り行ってもらいます。その他の仏具は閉眼供養の必要はありません。
売る前にきれいにしておく
仏具を売却する前には、できるだけきれいにしておくのがおすすめです。仏具がきれいな状態であれば、査定額が高くなる可能性があります。
特に仏壇そのものを売る場合には、引き出しの中もきれいに掃除しておきましょう。
昔の人は大切なものを仏壇に入れる傾向があり、引き出しに重要書類が入っている可能性があるためです。
仏具の買取相場

仏具の一般的な買取相場は以下のとおりです。
- ・仏像の相場は〜5万円ほど
- ・掛け軸の相場は〜1万円ほど
- ・おりんの相場は〜1万円ほど
- ・花立の相場は〜1万5千円ほど
- ・香炉・小香炉の相場は〜1万円ほど
- ・経机の相場は〜1万円ほど
仏具の買取価格は作家・素材・状態によって金額が変動するため、一概に上記の価格で買取できるとは限りません。
なかには大幅に上回るものや、価格がつかないものも存在します。詳細な金額は実際に査定してみなければ判断がつきません。
『買取むすび』では、仏具の買取を行っています。買取価格を知りたい方は、ぜひ無料査定をお試しください。
仏像の相場は〜5万円ほど
仏像の買取価格は、素材によって変動します。金を使用している場合は、含有量によって高額査定になる傾向です。
ただし、木製であっても、古美術品にあたるものは高値がつく場合もあります。
一般的には〜5万円程度が相場ですが、高価なものでは100万円を超える仏像も存在します。
掛け軸の相場は〜1万円ほど
掛け軸の買取相場は〜1万円ほどです。近年、和室・床間の減少など、住宅事情の変化に伴い買取価格はやや下降傾向です。
しかし、古美術品として評価されるものや、有名作家の作品などは思いがけない価格になる可能性があります。
おりんの相場は〜1万円ほど
おりんの買取相場は〜1万円ほどです。金製や金メッキが多いため、比較的価格がつきやすい仏具です。
純度や重量によっては、1万円以上で売れる可能性があり、純金の場合は数百万円もの価値を持ちます。
また、銀・プラチナのおりんも、高額査定が期待できます。
おりんについての詳細は、以下の記事でも解説しているため、ぜひ参考にしてみてください。
花立の相場は〜1万5千円ほど
花立の買取相場は〜1万5千円ほどです。純金や純銀の場合は、数十万円で取引される場合もあります。
有名な作家や窯元で作られた花立は、芸術品としての価値が高いため、高額買取が期待できます。
一方、有名作家の作品を模した偽物が出回っているため、売却する際は『買取むすび』のように専門家が在籍している買取専門店へ査定を依頼するのがおすすめです。
香炉・小香炉の相場は〜1万円ほど
香炉の買取相場は〜1万円ほどです。金・銀・真鍮で作られているものは、高く売れる可能性があります。
伝統工芸品としての価値も評価される場合もあり、なかには100万円を超える香炉・小香炉も存在します。
経机の相場は〜1万円ほど
経机の買取相場は〜1万円ほどです。素材や状態によって異なり、黒漆塗りや金箔が施されている経机は、高値がつく傾向です。
証明書が付属しているものは、さらに高く売れる可能性が上がります。素材が高級で状態がよい場合は、10万円を超える場合もあります。
仏具を売るなら「買取専門店」がおすすめ

仏具を売る方法は3つあります。
- ・オークションサイト・フリマサイト
- ・リサイクルショップ
- ・買取専門店
おすすめの方法は買取専門店です。
買取専門店の場合、仏具に関する専門知識を持った鑑定士によって査定が行われるため、適正な価格での買取が可能です。
特に高価な仏具を売りたい場合は、素材・作家・芸術面から査定できる買取専門店でなければ、安く査定されてしまう可能性があります。
オークションやフリマサイトでも高値で売れる可能性がありますが、落札者とのトラブルに発展するリスクがあるため、万人にはおすすめできません。
リサイクルショップは手軽に売却できるのがメリットではあるものの、すべてのショップが買取に対応していない点がデメリットです。
買取に対応していたとしても、価格が安い可能性があります。より高く売りたいのであれば、専門家が在籍している「買取専門店」へ査定を依頼しましょう。
『買取むすび』では仏具の高価買取が可能

『買取むすび』では、仏具の買取を実施しています。3つの買取方法を用意しているため、近くに店舗がない方や、来店する時間がない方もご利用可能です。
- ・店頭買取|予約不要で即日現金化が可能
- ・宅配買取|出張料無料で玄関先での査定も可能
- ・出張買取|送料無料で自宅にいながら査定可能
それぞれの特徴や、買取までの流れを紹介します。
店頭買取|予約不要で即日現金化が可能
店頭買取は、仏具を店舗までお持ちいただく方法です。来店予約は不要で、査定料・キャンセル料も発生しません。
専門知識を有した鑑定士が丁寧に査定し、適正な買取価格を提示いたします。成約となったら、その場で現金手渡しが可能です。
査定内容の詳細を鑑定士から直接聞けるため、初めて査定買取を利用する方におすすめです。
宅配買取|出張料無料で玄関先での査定も可能
宅配買取は、仏具を『買取むすび』に送るだけで査定・買取が完了する方法です。送料は弊社で負担し、ご希望の方には無料の宅配キットも用意しています。
査定結果は鑑定士から直接お電話し、成約となればご指定の口座に金額をお振り込みいたします。
査定結果を聞いた後にキャンセルしても手数料は発生しません。『買取むすび』で、責任を持って商品を返送いたします。(※返送料はお客様負担となっています)
近くに店舗がない方は、ぜひ宅配買取をお試しください。
出張買取|送料無料で自宅にいながら査定可能
出張買取は、『買取むすび』の鑑定士が自宅へ訪問し、品物を査定する方法です。出張料は発生せず、成約となったら、その場で現金払いが可能です。
玄関先での査定にも対応しており、キャンセルしても手数料は発生しません。
査定して欲しいものが多い方や、仏具を店舗に持っていくのが大変な方は、ぜひ出張買取をお試しください。
売却以外の処分方法

仏具は、自治体の分別に従って処分してよいとされています。使用されている素材に応じて、適切な方法で処分しましょう。
ただし、仏像や位牌などの礼拝対象の仏具は、閉眼供養をしてから処分する必要があります。
その他の仏具については、供養せずともゴミとして破棄して問題はありません。気持ち的に何かしたい場合は、お寺でお焚き上げしてもらうのもよいでしょう。
まとめ:仏具を売るなら『買取むすび』へ

『買取むすび』では、仏具の買取を実施しています。仏壇じまいや引っ越しなどで不要になった仏具があれば、気軽にご相談ください。
素材やデザインなどを丁寧に査定し、満足いただける価格を提示できるよう努めています。