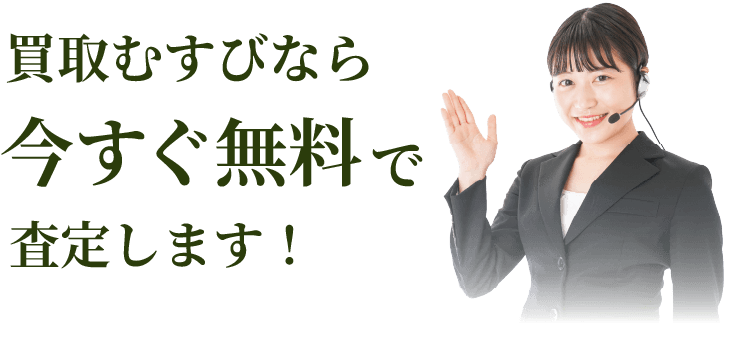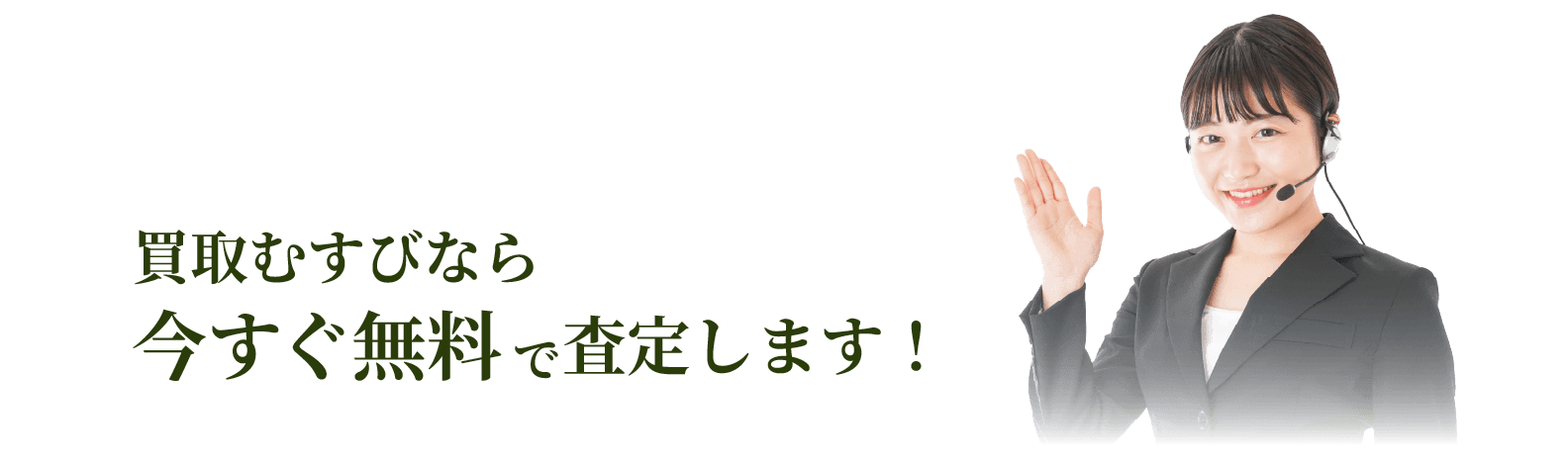執筆:
買取むすび 編集部
おりんとは?種類や素材を解説!高価買取が期待できるおりんも紹介

「おりんの特徴とは?」
「おりんを持っているけど売れるの?」
このようなお悩みはありませんか?
おりんは仏具の一つで、いくつか種類があり、素材によって音色が異なります。特に、素材次第では高価買取が期待できるため、不要なおりんの処分を検討されている方は、売却を考えてみるのも一つの方法です。
この記事では、おりんの歴史や種類を解説し、素材ごとの特徴や高価買取のポイントも紹介します。おりんについて知りたい方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
おりんとは

おりんは、仏壇に手を合わせたり、お経の途中で鳴らしたりする際に使用する仏具です。ここでは、以下の2つのポイントに焦点を当て、おりんの歴史を紹介します。
- ・おりんの起源や由来
- ・おりんを鳴らす意味
それぞれ見ていきましょう。
おりんの起源や由来
棒で叩くと「チーン」と音が鳴るおりんは「梵音具(ぼんおんぐ)」の一つです。梵音具とは音が出る仏具を指します。
現在どの宗派でも使用しているおりんの起源は、禅宗にあるとされています。禅宗とは、瞑想や坐禅に重点を置いた修行を行う宗派です。
また、おりんの由来は、お釈迦さまが亡くなったことを悲しんだ「リン」と呼ばれる鳥の鳴き声を再現したものだとされています。風鈴と音色が似ているため「りん」・「おりん」と呼ばれるようになったという一説もあるくらいです。
また、漢字では「輪」や「鈴」と表記され、呼び方は宗派や地域で異なります。宗派によっては「鏧(きん)」・「小鏧(しょうきん)」・「鐘(かね)」などと呼ぶ場合もあります。さらに、形・大きさ・素材・色・音色などの種類も豊富です。
おりんも含めた仏具全般については以下の記事で解説しているため、参考にしてみてください。
おりんを鳴らす意味
古くから、おりんの音色には邪念を払ったり、故人への気持ちを乗せて運んだりする意味があると信じられてきました。一般家庭では、仏壇に手を合わせる時に鳴らします。しかし、基本的にはお経を読み始める前・最中・終了時に鳴らすのが正しい使い方です。
また、鳴らす回数やタイミングなどの作法は、宗派やお住まいの地域によって異なります。鳴らす機会がある際は、作法を確認してみてください。
おりんの種類

近年、おりんは形や色のバリエーションが増え、モダンなデザインのものも登場しました。ここでは、以下の代表的な種類を紹介します。
- ・一般的な「鉢型」
- ・小型の「印金(いんきん)」
- ・グラスのような「高台りん」
一つずつ見ていきましょう。
一般的な「鉢型」
鉢型は、植木鉢やお椀のような見た目で、昔ながらの基本的な形です。仏壇に置く場合は「りん台」や「りん布団」に乗せます。りん台の装飾・りん布団のデザインは種類が豊富です。
また、おりんを叩くための専用の棒は「りん棒」と呼びます。持ち手を親指・人差し指・中指でつまむようにして持ち、縁の外側や内側を叩きます。叩く場所は宗派や地域によって異なるため、確認してみてください。
小型の「印金(いんきん)」
印金とは、鉢型のおりんに持ち手が付いた携帯用のものです。持ち手の先に小さなりん布団とおりんが付いているため、片手で持って鳴らせます。お墓参りや法要の際、おりんを置けない場合に使用するものです。
グラスのような「高台りん」
高台りんは、おりんにグラスの持ち手のような台が付いているものを指します。脚が付いているためりん台・りん布団は不要ですが、りん布団よりも薄い下敷きを敷くケースもあります。
おりんの素材

おりんは素材によって音色が異なります。使用される素材は主に以下の4つです。
- ・金
- ・砂張(さはり)
- ・真鍮
- ・シルジン青銅
それぞれの特徴を見ていきましょう。
金
金は仏具に使用されやすい金属です。金は、古くから高貴で敬意を払う対象とされてきました。金のおりんは高音で綺麗な音が出るのが特徴です。おりんのなかでは最高級品で、金の相場によっておりんの買取価格も変動します。
砂張(さはり)
砂張は銅と錫(すず)の合金です。沙張・佐波理・砂波理などと表記するケースもあります。一般的には金のおりんに次いで高価なため、状態次第で高価買取も期待できます。
砂張で作られたおりんは音が長く響き、音色が美しいのが特徴です。音が響く様子から「響銅(きょうどう)」とも呼ばれます。砂張は加工が難しい合金で割れやすいため、取り扱い時には注意が必要です。
真鍮
真鍮とは亜鉛と銅の合金で、黄銅とも呼ばれます。おりんの素材として一般的なものです。
真鍮のおりんは音の伸びが控えめで、比較的安価なため高価買取は期待できません。時間が経つと酸化し、黒ずんだり錆びたりするため、定期的なお手入れが必要な素材です。
シルジン青銅
シルジン青銅は、銅・亜鉛・ケイ素を含んだ合金です。ケイ素4〜5%を含んだ合金をシルジン青銅と呼びます。真鍮と同様に、素材として代表的なものです。真鍮よりも硬く、高価な砂張の代用品として使用されています。
金製品のおりんは高価買取も可能

仏具をそのまま処分することに抵抗がある方もいるかもしれません。お仏像やお位牌のように魂が宿るとされているものは「魂抜き」と呼ばれる供養を行います。しかし、おりんは魂が宿る仏具ではないため、自治体の処分方法に従って処分可能です。
金製品の仏具には貴金属やリサイクル品としての価値があります。素材によっては高価買取が期待できるため、処分する前に査定に出してみてはいかがでしょうか。
素材がわからない場合や本物の金か見分けが付かない場合の鑑定は、ぜひ『買取むすび』におまかせください。金製品は金の種類や含有量によって査定額が変わります。以下の記事にまとめているため、ぜひ参考にしてみてください。
おりんのお手入れ方法と注意点

綺麗な状態の品物は査定額がアップする可能性があるため、査定前にお手入れするとよいでしょう。お手入れは乾拭きが基本です。
また、素材によって適切なお手入れ方法が異なります。例えば、真鍮のものは酢を使った錆落としや専用の磨き剤でのお手入れが有効です。
一方、色が塗ってあるもの・メッキ加工されているものは、コーティングが剥がれる恐れがあるため磨き剤は使えません。素材がわからない場合は、仏具店に相談する方法もあります。
おりんを売るなら『買取むすび』におまかせ

『買取むすび』ではおりんも買取対象です。終活・断捨離・遺品整理・生前整理などで、不要なおりんがある場合はぜひご相談ください。
『買取むすび』には以下の特徴があります。
- ・遺品整理・生前整理の実績が豊富
- ・【相談・査定は無料】買取方法が選べる
それぞれ解説します。
遺品整理・生前整理の実績が豊富
『買取むすび』では、終活や遺品整理で不要となった品物の査定を実施しています。ご家族に残すべきものや売れるものの判別ができない場合の相談も可能です。まずは無料査定をお試しください。
不要品のなかに、高価買取が期待できるものが含まれている可能性があります。高く売れるかもしれないものについては以下の記事で紹介しているため、ぜひ参考にしてみてください。
【相談・査定は無料】買取方法が選べる
『買取むすび』は相談料・査定料が無料なため「売れるかわからない」と不安な場合も、ぜひご相談ください。また、3つの買取方法から、ライフスタイルに合ったものを選べます。それぞれの買取方法の特徴は以下の通りです。
|
買取方法 |
特徴 |
|
|
|
|
|
また、スマホから送信するだけで査定可能なLINE査定、査定・買取についての相談ができるメール査定も便利です。
まとめ:不要なおりんはぜひ『買取むすび』へ

『買取むすび』では、おりんを含む遺品や不要品の買取が可能です。汚れや破損がある品物も買取できます。相談や査定は無料のため、おりんの処分に困っている方はぜひ『買取むすび』にお越しください。