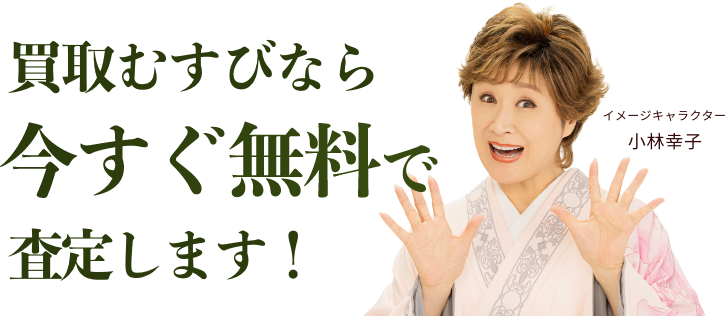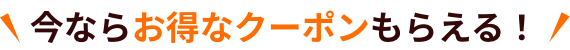金の売却にかかる税金とは?貴金属や宝石の場合も解説

金の価格は年々上昇傾向にあり、2022年現在も高値で取り引きされています。
そのため、金を売却する際課税額もより大きくなる可能性が高く、課税の有無やいくら課税されるのかという点をしっかりと把握しておきたいものです。
そこで本記事では、金および貴金属、そして宝石の売却に際しての課税の有無や税額の計算方法をまとめました。
金や貴金属、また宝石の売却を検討されている方は、ぜひ最後までご覧ください。
目次
金の売却で課税の対象になる所得区分
金の売却で得られる所得は3つの所得区分に分けられますが、それぞれの所得区分によって所得税の計算のされ方などに違いがあります。
そのため、金を売却することで得られる所得がどの所得区分に該当するのかを、しっかりと確認しておきましょう。
ここでは、金を売る場合に確認しておきたい、3つの所得区分の定義をそれぞれ解説します。
区分①譲渡所得
譲渡所得とは、所有する資産を第三者に譲渡することによって生じる所得のことです。
一般的に、個人が所有していた金を売却することで得られる所得は譲渡所得とみなされ、所得税が課せられます。
区分②事業所得
事業所得とは、その名の通り事業を営むことによって生じる所得のことです。
企業や個人事業主などの事業者が、営利を目的として継続的に金を売買し、それによって得られた所得は事業所得とみなされ、所得税が課せられます。
区分③雑所得
雑所得とは、国が定めた10の所得区分のうち、譲渡所得や事業所得を含むほかの9つの区分に当てはまらない所得のことです。
たとえば、非営業用貸金の利子や、副業によって得られる所得が雑所得に区分されます。
金の売却においては、個人が営利目的で継続的に金を売却し所得を得ている場合が該当し、このケースで得られる所得は個人であっても雑所得とみなされることがあります。
なお、この雑所得も課税の対象です。
雑所得は、今回挙げた3つの所得区分のなかでもっとも珍しいケースといってよいでしょう。
貴金属や宝石を売却する場合も所得税の課税の対象になる?
貴金属や宝石は「生活用動産(生活に必要な品)」とみなされるため、原則、これらの売却で得られる所得は課税の対象外です。
ただし、貴金属や宝石であっても、売却金額が1点あたり30万円を超える品の場合は資産と見なされ、所得税が課せられます。
参考記事:18金と24金はどっちが高い?特徴と違いを詳しく紹介
金の売却で得られる譲渡所得に対する所得税額の計算方法
金を売却して得られる譲渡所得に対する所得税額は、金を所有した期間によって異なってきます。
なぜなら、所有期間によって所得税額の計算方法も異なるためです。
ここでは、金の売却によって得られる所得に対する所得税額の計算方法を、所有期間別に紹介します。
なお、一般的には、個人が金を売却することで得られる所得は譲渡所得に分類されるため、今回は所得の区分が譲渡所得の場合とした前提で解説します。
所有期間が5年未満の場合
金を購入してから5年未満で売却する場合に得られる所得のことを、「短期譲渡所得」とよびます。
この短期譲渡所得の所得税額を計算するためには、まずは下記の計算式で金の売却による利益である「譲渡益」を算出する必要があります。
金の譲渡益=(金の売却金額)-(金の取得金額+金の売却費用)…①
なお、取得金額とは金の購入金額であり、売却費用とは金を売却する際に発生する手数料などの費用のことです。
金の譲渡益をもとめたら、続いて課税対象の所得の金額を算出します。
課税の対象となる所得=(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-(特別控除50万円)…②
なお、その他の譲渡益は、たとえばFX売買などで得た利益のことです。
計算式②では、金の売却によって得られる利益である譲渡益を、その他の譲渡益と併せて、課税対象の所得を算出しています。
最後に、計算式②で算出した課税対象の所得の金額に、所得税の税率を乗じることで、所得税額を算出することができます。
所有期間が5年以上の場合
金を購入してから5年以上経ったのちに、金を売却する場合に得られる所得のことを「長期譲渡所得」といいます。
譲渡益の算出方法は短期譲渡所得の場合と同様ですが、所得税額は短期譲渡所得の場合と比べて2分の1と決められています。
長期譲渡所得の課税対象の所得の金額の計算方法は、下記のとおりです。
課税対象の所得=〔(金の譲渡益)+(その他の譲渡益)-(特別控除50万円)〕×1/2
計算式で算出した課税対象の所得の金額に、所得税の税率を乗じたものが所得税額です。
計算式で示したとおり、金を売却する場合は短期譲渡所得よりも長期譲渡所得のほうが課税される所得税額が少ないという点を覚えておきましょう。
金を売却して損失が出た場合の通算の方法
もし、金を売却して損失が出てしまった場合、所得税の課税はどのように行われるのでしょうか?
金を売却して損失が発生した場合は、「通算」を行うことが可能です。
通算とは、簡単にいうと赤字と黒字を相殺することです。
つまり、たとえば金の売却で損失が出てしまった場合は、株式などで得たほかの利益と相殺することで、所得税の納税額を軽減することができます。
ここでは、金を売って損失が出てしまった場合の通算の方法を、所得の区分別に解説します。
区分①譲渡所得
譲渡所得で損失が出た場合は、同じ年の1~12月のあいだで発生したその他の譲渡所得とのみ通算することが可能です。
このように、同じ区分の所得同士を通算することを「内部通算」とよびます。
たとえば、株式で200万円の利益を出し、同じ年に金の売却では50万円の損失を出した場合、通算を適用したうえでの譲渡益は下記のとおりとなります。
200万円(株式の売買による利益)-50万円(金の売却による損失)=150万円(譲渡益)
上記の式で算出した譲渡益である150万円から、特別控除額の50万円を差し引いた金額である100万円が、最終的な課税対象の金額です。
150万円(譲渡益)-50万円(控除額)=100万円(課税対象の金額)
区分②事業所得
事業所得で損失が出た場合は、ほかの所得の利益と通算が可能です。
このように、ほかの区分の所得の利益と通算する方法を「損益通算」とよびます。
(金を売却して発生した事業所得の損失)-(その他の所得の利益)=(課税対象の金額)
区分③雑所得
雑所得で損失が出た場合は、同じ年に発生したほかの雑所得とのみ、通算が可能です。
(金を売却して発生した雑所得の損失)-(その他の雑所得の利益)=(課税対象の金額)
参考記事:金を高く売るタイミングは?売り時を見極めるコツを紹介
金の売却をご検討なら「買取むすび」にお任せください!
金の価格は高騰し続けており、 2022年10月現在、20年前の10倍以上の価格で取り引きされています。
もし、ご自宅に眠っている金があるという方は、ぜひ一度「買取むすび」の無料査定をご検討ください。
「買取むすび」では、金歯に使われている金や、壊れてしまったアクセサリーの金でも買い取らせていただいております。
「これはさすがに売れないだろう。」と思われるような品物や、他店で買い取りを断られたお品物でも、まずはお気軽にご相談ください。
また「買取むすび」では、プロの鑑定士による無料の査定を行っており、他社を圧倒する高価買い取りの実績が多数ございます。
なお、買い取りが決まった際は、即日現金払いをさせていただきます。
ご自宅に不要な金があるという方や、もしくはすでに金の売却をご検討されている方は、ぜひ「買取むすび」へお問い合わせください。
お電話やLINE、またはメールにてご相談および無料査定を実施しております。
正しい税金の知識をもったうえで金の売却を行いましょう
いかがでしたでしょうか?
現在、金の価格は上昇を続けており、売却にあたっての所得税額も高額になる可能性が高いため、しっかりとした税金の知識をもっておくことが大切です。
金の売却によって得られる所得に対する所得税額は、該当する所得区分や、金の所有年数によって異なります。
また、金の売却で損失が出てしまった場合は通算を適用することが可能です。
納得のいく金の売却を実現するためにも、ぜひ本記事をご参考いただければ幸いです。
「買取むすび」では不要になった金の無料査定を行っております。
高価買い取り実績も多数ございますため、まずはお気軽にご相談ください。